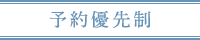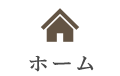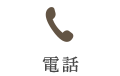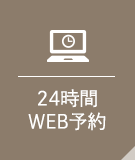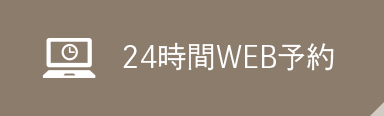ピロリ菌とは
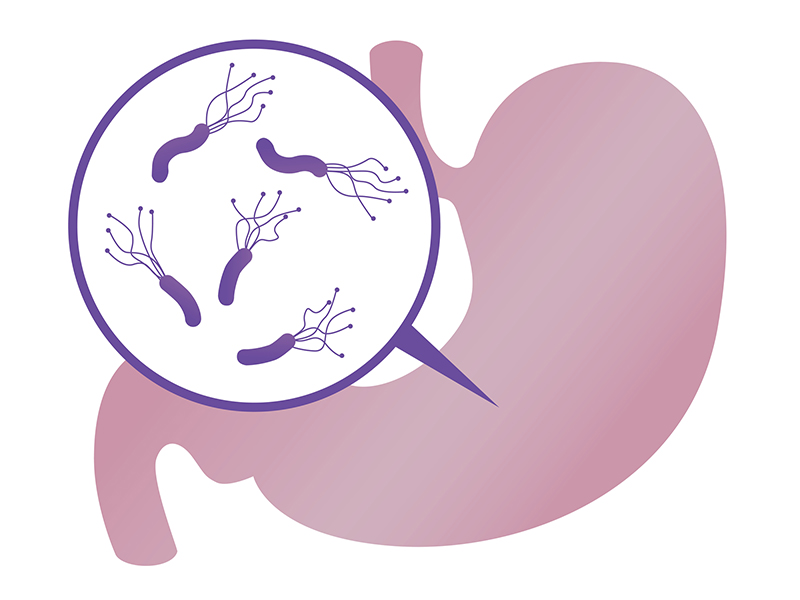
ピロリ菌に感染すると胃粘膜が慢性的な炎症を起こし、胃潰瘍・十二指腸潰瘍や胃MALTリンパ腫、紫斑病などの原因となります。また慢性的な胃炎が進行して萎縮性胃炎になると胃がん発症リスクが大幅に上昇してしまいます。
ピロリ菌の感染
衛生環境が悪いと井戸水などを介して感染すると考えられていて、感染は主に幼少期に起こり、成人してから衛生環境の悪い場所に住んでも感染することはほとんどありません。日本では高齢者の感染率はまだ高い状態が続いていますが、若い世代の感染はかなり少なくなってきています。ただし、ヒトからヒトへの感染も幼少期の口移しなどで起こる可能性があることが指摘されています。
ピロリ菌に感染していても除菌治療を成功させることでピロリ菌を除去できます。これによって炎症や潰瘍の再発も起こりにくくなります。
ピロリ菌感染を調べるための検査
ピロリ菌の感染検査は6種類あって、胃カメラ検査で組織を採取するものと、そうではないものに大きく分けられます。
内視鏡を使う検査
胃カメラ検査時に胃の組織を採取して回収し、下記の検査を行います。
| 培養法 | 胃の粘膜をすりつぶし、5~7日培養して判定します。 |
|---|---|
| 迅速ウレアーゼ法 | ピロリ菌が持つ酵素のウレアーゼの働きによってアンモニアができるかどうかを調べます。 |
| 組織鏡検法 | 採取した組織に特殊な染色をして顕微鏡で観察して調べます。 |
内視鏡を使わない検査
| 尿素呼気試験法 | 検査薬の服用前・服用後の呼気を採取して検査します。 ピロリ菌が持つ酵素のウレアーゼの働きによって作られる二酸化炭素の量を測定します。 内視鏡を用いない検査の中では精度が高い方法です。 |
|---|---|
| 抗体測定法 | 尿や血液を採取してピロリ菌に対する抗体の有無を調べます。 |
| 抗原測定法 | 便を採取してピロリ菌抗原の有無を調べます。 |
ピロリ菌除菌治療

通常、最初に行われる1次除菌ではアモキシシリンとクラリスロマイシンという抗生剤を使います。ピロリ菌除菌治療は100%成功するものではなく、失敗することがあります。一時除菌に失敗した際に行われる2次除菌や、先の抗生剤がアレルギーで使用できない場合には、抗生剤の種類を変更して治療が行われます。
なお、1次除菌では80%前後が成功し、1次除菌と2次除菌を含めた成功率は約98%とされています。
保険適用について

ピロリ菌の検査・治療についてご不明点やご質問がありましたら、お気軽にご相談ください。